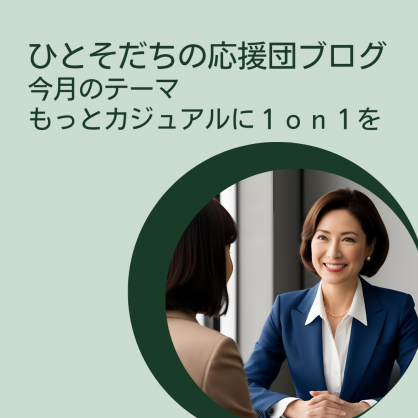新人研修のあとでちょっとだけ思ったこと その1
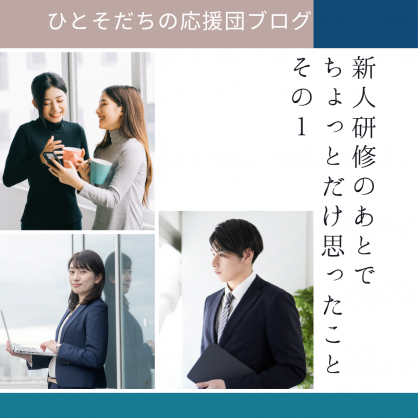
毎年のことながら4月は新入社員研修が目白押しでした。
講師にとっては、とりわけ神経を使います。
全く白紙の新社会人に対して、
決して自信を無くさせてはいけないと強く感じているからです。
これからの明るい未来に向かって希望をもって進んでほしいからです。
おかげで講師たちは新入社員の皆さんから、
たくさんのプレゼント(学びや気づき)をもらうこともあります。
今回はその中の一部を紹介します。
今回から数回にわたってお届けします。
プレゼント その1
中小企業で、少人数の新入社員研修を担当したときのことです。
対象は全員20代前半の新社会人。
終日、「社会人としての基礎力」と「ビジネスマナー」について
お伝えしました。
長時間の研修で疲れたり飽きたりしないよう、
途中にはペアワークやコミュニケーションゲームも取り入れました。
少人数だったこともあり、一人ひとりの様子を丁寧に見ることができ、
細かなミスがあればその場で具体的に指摘し、
正解が導けた時には、全力でほめました。
講師としても、とてもやりがいを感じる時間でした。
研修の最後に、参加者一人ひとりに感想を話してもらいました。
「正しい言葉遣いを知れてよかったです」
「名刺交換の手順が分かりました」
「営業の仕組みが理解できました」
といった感想が続き、順調に進んでいたのですが・・・
最後の一人が、少し照れながらもこう言いました。
「講師の先生がすごく楽しそうに仕事をしていて、
仕事って楽しいものだと分かりました」
少し驚いて、「え?私が楽しそうだったのが印象に残ったの?」と聞き返すと、
満面の笑みでこう言ってくれました。
「はい!先生、本当に楽しそうでした。
私は正直、仕事って大変なもの、辛いものだと思っていました。
でも、先生が一日中楽しそうに仕事をしているのを見て、
好きな仕事をするってこんなに楽しいことなんだ、
と気づきました。ありがとうございました」
胸がいっぱいになりました。
研修終了後、新入社員と同じく
終日立ち会ってくださっていた人事担当の方が、
私に話しかけてくださいました。
「もしかしたら、私たち上司や先輩は、
新人たちに『仕事は大変なもの』『辛くてもやらなきゃいけないもの』という姿しか
見せられていなかったのかもしれません。
先生が全力で叱ったり、
全力でほめたりしてくれたように、
私たちも『この仕事って実は楽しいんだよ』
『この仕事にはこんなやりがいがあるんだよ』ということを、
職場の中で自然に伝えていくことが大切なんですね。
今日は大きな気づきをありがとうございました」
新入社員と向き合う時間は、
未来と向き合う時間でもあります。
だからこそ、こちらの姿勢や言葉一つひとつが、
彼らにとっての“仕事の原風景”になるのかもしれません。
そして、ふと思いました。
新入社員にとって、「仕事って楽しいんだよ」と伝えてくれる先輩は、
どれだけいるでしょうか?
気づけば、先輩たちが見せているのは
「大変さ」や「忙しさ」ばかりかもしれません。
もちろんそれも現実ではありますが、
そこに「楽しさ」や「やりがい」も含まれていること、
それを先輩が自分の背中で伝えていくことが、
何よりの関わり方なのではないか・・・
今回の研修を通じて、そんなことを学ばせてもらった気がします。
新入社員と接することで、既存の社員もまた、
新たな気づきや自分のあり方を見直す機会をもらっているのだと感じました。
教えることで学ぶ。
それを、まさに実感した一日でした。